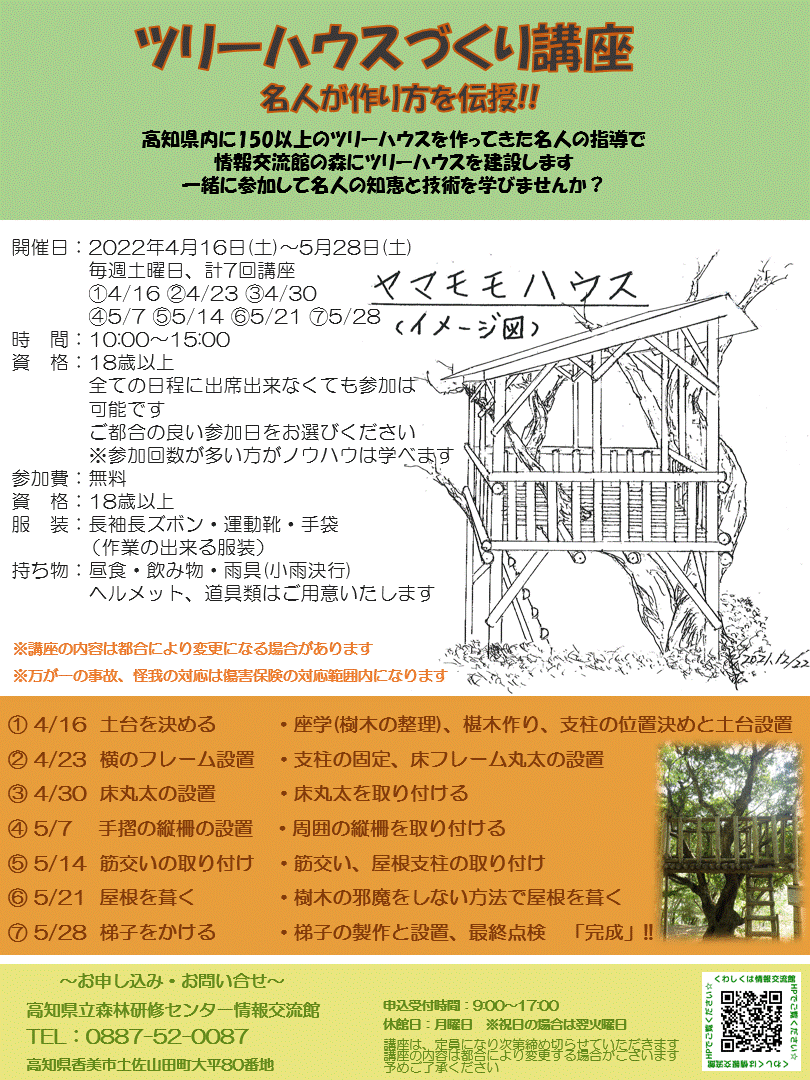情報交流館主催ではありませんが、こちらの施設で開催される講座のご紹介です
ツリーハウスづくり講座も8回目となりました。
まずは残り一枚となった屋根の取り付けと、はしご回りの滑り止めと柵を取り付けていきます。
屋根周りはヤマモモの枝が出る様に丸くガルバリウムを切り、周りを囲っていきます。 階段周りに柵と滑り止めを付けていきます。
階段周りに柵と滑り止めを付けていきます。 屋根と滑り止めと柵が完成しました!最後に飛び出した傘釘をカットしていきます。
屋根と滑り止めと柵が完成しました!最後に飛び出した傘釘をカットしていきます。
完成です!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



怪我もなく全8回のツリーハウスづくり講座を終える事ができ、とても素晴らしいツリーハウスが完成しました。皆さんお疲れさまでした。今回の講座で学んだことを活かして、皆さんもツリーハウスを建ててみましょう!
5月14日第5回ツリーハウス作り講座を開催しました。
天気も回復し晴天となったツリーハウス作り講座、早くも5回目となりました。今回は床を貼り滑り止めを取り付ける工程を行いました。
まず床に敷く丸太にドリルで固定用の下穴を開けていきます。 下穴を開けた丸太をコーチボルトで固定していきます。丸太が浮かないよう体重をかけて押さえます。丸太は少し間隔を開けて固定し落ち葉や水が溜まらないよう工夫しています。
下穴を開けた丸太をコーチボルトで固定していきます。丸太が浮かないよう体重をかけて押さえます。丸太は少し間隔を開けて固定し落ち葉や水が溜まらないよう工夫しています。 はしごの位置決めをして
はしごの位置決めをして 滑り止めを四方に固定していきます。下穴を再度ドリルで掘り大きくして半ねじボルトで固定していきます。
滑り止めを四方に固定していきます。下穴を再度ドリルで掘り大きくして半ねじボルトで固定していきます。 床と滑り止めが完成しました!
床と滑り止めが完成しました!
次回、はしご作りから手すりの取り付け作業です。完成目指して頑張りましょう!
情報交流館のツリーハウスを建設するにあたってツリーハウス作りの技術や知恵を学ぼうと4月16日(土)から5月28日(土)まで毎週土曜日に計7回に分けてツリーハウス作り講座を開催します。講師は県内に150以上のツリーハウスを作ってきた名人、浜氏 拡(はまうじ ひろし)さんです。
第一回講座4月16日(土)
まず座学で樹の生態やツリーハウスを作るにあたっての心構えを学びます。
今回の講座ではツリーハウスの構造などを理解するために、老朽化したツリーハウスの解体から始めます。バール、かけや、インパクトドリルなどを使い順に解体していきます。 解体が終わったら、三四五定規を使い柱の位置を正四方形に位置決めし土台となる沓石(くついし)を埋設し第一回講座は終了です。
解体が終わったら、三四五定規を使い柱の位置を正四方形に位置決めし土台となる沓石(くついし)を埋設し第一回講座は終了です。
第二回講座4月23日(土)
前回埋設した土台となる沓石の直角と水平出しからの作業です。レーザー水平器などを使って作業をしていきます。皆さん初めての作業に試行錯誤しながら水平を出していました。 次に支柱となる丸太を加工します。今回利用する丸太は長さが足りないので継いで利用します。墨付けをして加工していきます。手ノコで30cm縦挽きするので大変です。第二回の作業はここで終了です。
次に支柱となる丸太を加工します。今回利用する丸太は長さが足りないので継いで利用します。墨付けをして加工していきます。手ノコで30cm縦挽きするので大変です。第二回の作業はここで終了です。
次週は組み立てに入る予定です。どんなツリーハウスになるのか楽しみですね!
4月10日「刈り払い機初心者講座」を開催しました。
この講座では刈り払い機を使ってみたい、使い方に自信がない、習いたいが資格講習などは敷居が高いといった方のために基本的な取り扱い方を作業を通して学んでいただきます。講師は「森の元気!お助け隊」の皆さんです。
当日の様子はKUTV「がんばれ高知!!eco応援団」で放送されます。お楽しみに!
次回の「刈り払い機初心者講座」は9月開催予定です。
実際に刈り払い機を使って操作を覚えていきます。操作時のコツや気をつける事など沢山のノウハウを講師のお助け隊の皆さんが教えてくれます。

皆さんどんどん上達して午前中と午後では見違えるようでした。
~受講者の声~
「最初は戸惑ったが時間がたつと慣れてきて楽しくなりました。」「思ったよりも沢山刈れ、機械にも慣れることが出来ました。」「講師の方がマンツーマンで教えてくれるので安心安全で、すぐやり方のコツを教えてくれるのでわかりやすかったです。」「使い始めは怖かったですが、慣れてくると草が刈れる事が気持ちよく楽しかった。」
皆さん真剣に聞き講師に質問もされていました。操作にも慣れ上手に取り扱うことが出来る様になっていたと思います。自宅での作業の際も今回の講座で学んだことを活かして安全に刈り払い機を取り扱ってください。



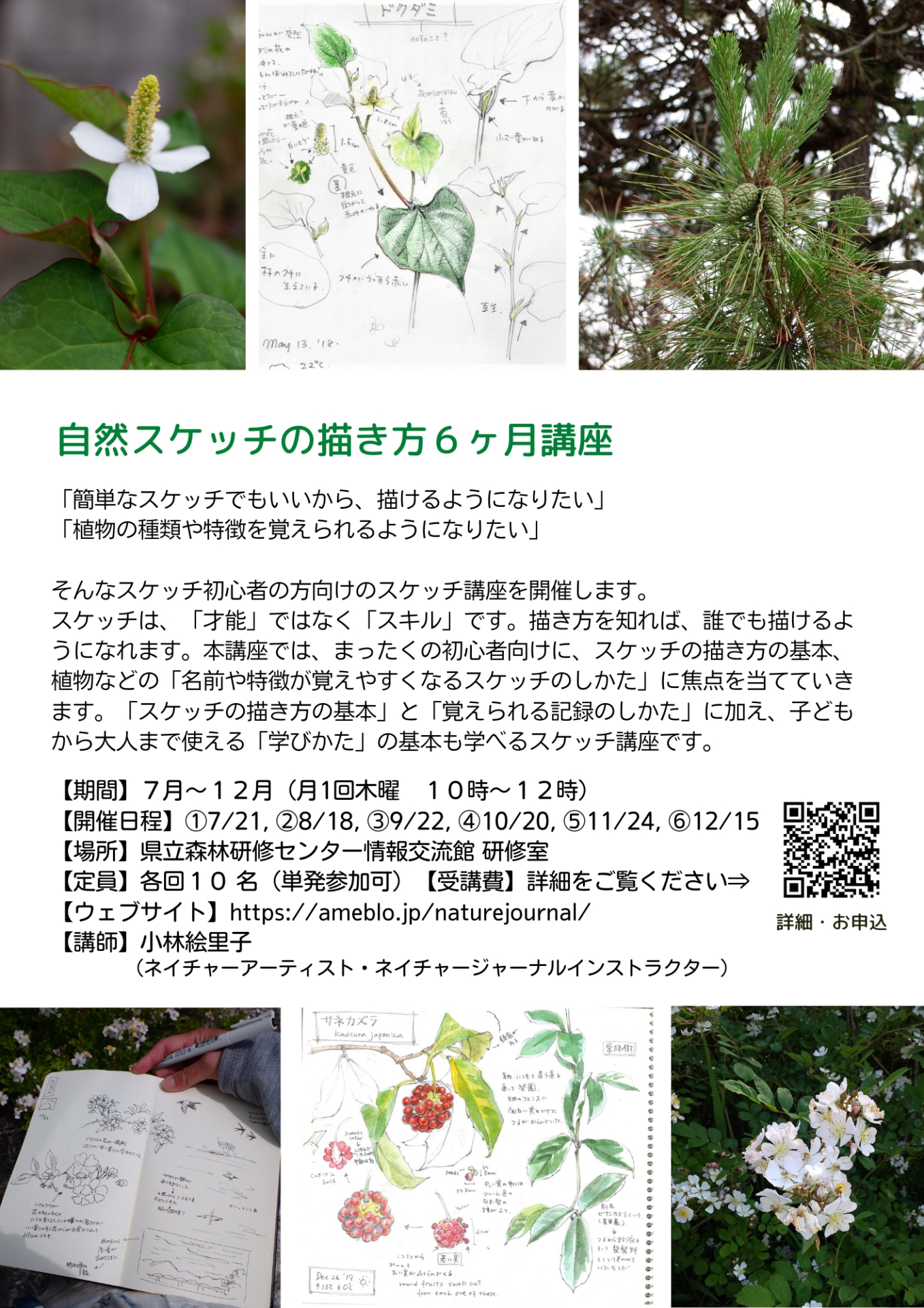


 同時進行で屋根側に付ける筋交いを作っていきます
同時進行で屋根側に付ける筋交いを作っていきます

 屋根のガルバリウムに傘釘を打つ位置を決めていき、ヤマモモの枝が通る穴を作ります
屋根のガルバリウムに傘釘を打つ位置を決めていき、ヤマモモの枝が通る穴を作ります あと少し!
あと少し!
 ノミとノコギリを使って、はしごを作っていきます。
ノミとノコギリを使って、はしごを作っていきます。 足場を作り柱の余分を切り落とした後、梁を乗せる部分を削ります。3mの梁を皆で担ぎ上げ固定していきます。
足場を作り柱の余分を切り落とした後、梁を乗せる部分を削ります。3mの梁を皆で担ぎ上げ固定していきます。 今回の作業はここまで。完成まであと少しです!
今回の作業はここまで。完成まであと少しです!
 合うかどうか確認しつつ加工を進めます。
合うかどうか確認しつつ加工を進めます。 柱が真っ直ぐになっているか確認しながら筋交いを取り付けます。
柱が真っ直ぐになっているか確認しながら筋交いを取り付けます。 他の筋交いもどんどん作り取り付けていきます。
他の筋交いもどんどん作り取り付けていきます。 筋交いを取り付けたら次は、床を取り付けていきます。
筋交いを取り付けたら次は、床を取り付けていきます。




 骨組みの柱を固定する為のボルトを通す穴を開けていきます。
骨組みの柱を固定する為のボルトを通す穴を開けていきます。 四隅のボルトを固定して組み上げ骨組みの完成です。
四隅のボルトを固定して組み上げ骨組みの完成です。